|
上映作品一覧 |
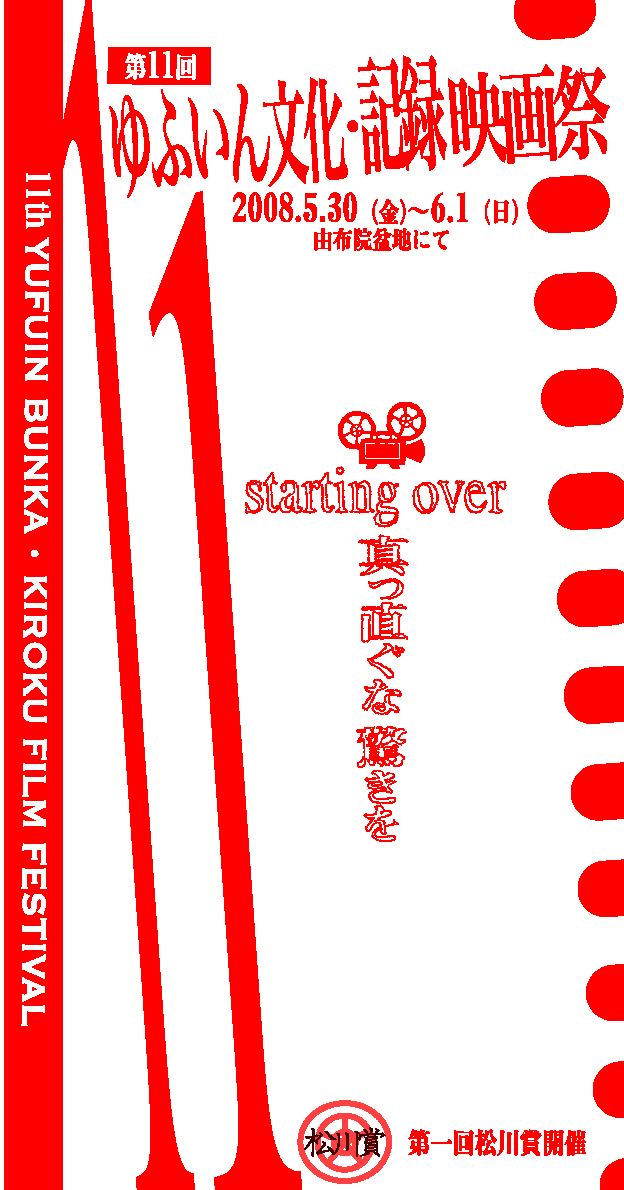
|
2008年5月30日(金)前夜祭 |
|
プログラムA 作品上映 18:30〜20:00 ゲストトーク 20:00〜20:30 |
『本多静六〜いのちを育てる森の実学』 2007年/46分/カラー/VIDEO 制作:ポルケ 企画・発行:紀伊國屋書店 脚本・監督:萩生田宏治 撮影:住田望、落合智成 語り:柄本明、仲里依紗 プロデューサー:住田望、佐野司 世紀を越えた視野を持って社会の中で生きた学者、本多静六。明治神宮の森、水源林、日比谷公園、そして由布院。彼の探究は学問の垣根を越えて広がり続け、それは常に社会に実を結ぶ学問、実学として貫かれていた。「木が二本あればそこは林学者の仕事場です」。幾多の挫折から努力を重ね、未来を見定めながら時代の要求に応え続けた生涯。天然更新、独立自強……、その実践から学んだ教訓を、私たちの世紀へと投げかけ続けた。人生即努力、努力即幸福。森を育て、街を育て、そして人を育てた命の学問の実践者である本多静六から未来の社会のありかたを考えていく。 『心に響け いのちの授業』 2007年/43分/カラー/VIDEO 制作:NHK京都放送局 ディレクター:柄子和也 撮影:高津裕治 音声:李 成秀 語り:大沼ひろみ 制作統括:大森龍一郎 大分県豊後高田市、全校生徒39人の河内中学校。ここに去年10月、28年間思春期の子どもたちに正面から向き合ってきた保健室の先生、山田泉さんが戻ってきた。山田さんは一昨年、乳がんを再発し一度は退職も覚悟したが、手術を受け、投薬治療を続けながら1年半ぶりに職場復帰した。ところが生徒たちの無反応な態度やぎくしゃくした人間関係に直面し て心を痛める。そこで多感な中学生が命の重さについて考え、自らの生き方や周囲への態度を見つめ直して欲しいとがんを患ってから取り組んできたライフワーク、「いのちの授業」を始めた。中学生の心に山田さんのメッセージは届くのか。試行錯誤を繰り返しながら、揺れ動く生徒たちに寄り添おうとするひとりの教師を見つめる。 |
| ゲストトーク:山田泉さん(元中学校教諭) |
|
2008年5月31日(土) |
|
プログラムB 作品上映 10:00〜11:40 |
『日本の稲作 〜そのこころと伝統』 1974年/42分/カラー/16mm 制作:英映画社 企画:文化庁 脚本・監督:青山通春 撮影:宮下英一 音楽:真鍋理一郎 プロデューサー:高橋銀三郎 日本人は稲作を基調とする民族で、日本人の生活・文化を考えるうえで稲作は切離せない関 係にある。生活の<近代化>とともに次第に滅び行く旧来の稲作とその祭り行事や伝統を、 約一年半にわたって日本全国を北から南へと取材し、構成した労作。 『山かげに生きる人たち』 1961年/51分/白黒/16mm 制作:英映画社 脚本・監督:青山通春 脚本:西岡豊 撮影:黒田清巳 音楽:林光 出演:加藤忠、眞木小苗、和沢昌治、野辺かほる、森幹太 プロデューサー:高橋銀三郎 僻地にあって、教育や娯楽、医療に恵まれない人々が、悪条件と闘いながら真剣に生活していくさまを詩情豊かに描いた作品。 |
|
プログラムC 作品上映 12:30〜14:20 ゲストトーク 14:20〜15:00 |
『夜明けの国』 1967年/110分/カラー/16mm 制作:岩波映画製作所 監督:時枝俊江 脚本:吉原順平 撮影:藤瀬季彦、渡辺重治 音楽:三善晃 プロデューサー:高村武次 北京、瀋陽、撫順、鞍山、長春、ハルピンを中心に、中国東北部の人々の生活を多面的に捉えた長篇。文化革命の始まった1966年8月から67年2月まで6ヶ月にわたるロケーションを敢行し、撮影フィルムが約8万フィートに及んだという。中国人の生活を撮るために入国したその日に中国共産党が文化大革命についての声明を出した。モンタージュはせずに見たままの中国を記録した文化大革命初期の貴重な作品。 |
| ゲストトーク:時枝俊江さん(「夜明けの国」監督) |
|
プログラムD 【産業・科学技術映画特集】 テクノロジー万華鏡! 作品上映 15:00〜16:20 ゲストトーク 16:30〜17:00 |
『五重塔はなぜ倒れないか』 2006年/35分/カラー/VIDEO 制作:日映企画 監督:浅野光彦 脚本:田部純正 撮影:藤崎彰 語り:江守徹 プロデューサー:中嶋康勝 世界最古の高層木造建築・法隆寺の五重塔。五重塔の立つ風景、それは日本人の心の風景であろう。 千年の時を超えて受け継がれてきた匠の技は、現代社会に大きな影響を与え、建築技術のさまざまな分野に新鮮な刺激を与えている。五重塔はなぜ倒れないか…。法隆寺以前から江戸時代までの五重塔を取材してその耐震性の秘密を現代工学の手法で解き明かそうとする試みを迫った作品。 『胃 〜巧妙な消化のしくみ』 2006年/14分/カラー/VIDEO 制作:アイカム 企画:あすか製薬 構成:武田純一郎 監督:玉井潤 脚本:川村智子、玉井潤 撮影:林正浩、北原幸夫、他 研究:富田勉 石崎美知子 CG:永田雅己 語り:伊藤惣一 プロデューサー:武田純一郎 強力な胃酸とペプシンで食物を消化する胃。しかし胃は、なぜ自分自身を消化しないのだろうか?胃は、内側を覆う粘液によって消化作用から守られているというが、実は、その詳細は未だ明らかにされていない。この古くて新しい謎を解き明かすため、胃酸分泌の過程を映像で記録することを試みた。 『3万kmの瞳〜宇宙電波望遠鏡で銀河ブラックホールに迫る』 2005年/30分/カラー/VIDEO 制作:イメージサイエンス 企画:JAXA 宇宙科学研究本部 脚本・監督:牧口光郎 撮影:坂田祐次 プロデューサー:渡辺昇 望遠鏡の解像度を極限まで高めようという電波天文学者の夢が、地球よりも大きな直径3万kmの宇宙 電波望遠鏡を実現させ、銀河の驚くべき現象をとらえた。電波天文衛星「はるか」と地上電波望遠鏡に よる壮大な宇宙電波干渉計プロジェクト「VSOP」が実現されていく過程と、その科学成果をまとめた作品。 |
| ゲストトーク:池内了さん(宇宙物理学者) |
|
プログラムC 作品上映 18:00〜20:00 ゲストトーク 20:00〜20:30 |
『出草之歌ー台湾原住民の吶喊 背山一戦』 2006年新編集版/112分/カラー/VIDEO 制作:NDU 日本ドキュメンタリストユニオン 配給:プラネット映画資料図書館 監督・撮影・編集:井上修 日本の植民地時代、皇民化教育を受けた台湾原住民は「高砂義勇隊」として戦場に駆り出され、そのあげく一方的に靖国神社に祀られた。その先祖の魂を奪還すべく闘う彼らの運動の中心には、原住民の生活と伝統に根ざした<歌>が最大の武器としてある。列強国の支配に翻弄され続けた台湾原住民が、「国家」という概念に鋭い問いを投げかける。 |
| ゲストトーク:井上修(「出草之歌」監督) |
| 2008年6月1日(日) |
|
プログラムF 作品上映 11:00〜12:30 13:30〜15:50 授賞式 16:30〜17:50 |
【第1回「松川賞」入賞作品上映】 『津軽の地蔵(ジンジョ)さま』 国立歴史民俗博物館(大峠プロダクション) 2007年/30分/カラー/16mm 制作:大峠プロダクション 企画:国立歴史民俗博物館 脚本・監督:鈴木康敬 脚本:菅野均 撮影:八幡洋一、佐藤文男 音楽:光永龍太郎 語り:藤夏子 プロデューサー:大峠幸雄 青森県・津軽地方では、地蔵さまのことを親しみを込めて「ジンジョさま」と呼ぶ。津軽では地蔵さまを守るのは女たちの仕事で、集落の安全を祈る行事も担っている。そんな「みちのく津軽」の地蔵(じんじょ)さまと地域の人々との交流の記録。 『茨の同盟』 吉田和史 2006年/60分/カラー/VIDEO 制作:早稲田大学川口芸術学校 監督:吉田和史 撮影・録音:石河雅史、土田潤也 編集・音楽:吉田和史 女優・沢田亜矢子との離婚騒動をきっかけにマスコミに登場し、その後も歌手デビュー、ホスト転身、整形手術、プロレスデビューなどの活躍でワイドショーをにぎわしてきたゴージャス松野。彼が2005年9月に故郷福島で主催したプロレス興行「ゴージャスナイト」開催までの道のりを追ったドキュメンタリー。 『色彩の記憶』 ケイビープランニングインターナショナル 2007年/30分/カラー/VIDEO 製作:ミルボン・KBP 企画:佐藤龍二・桂良一 プロデューサー:井手口直樹/ 監督:御法川修 日本磁器発祥の地、佐賀県有田。陶工・馬場真右ェ門は、絵付け、白磁が中心の有田焼の中で、窯変もの、中でも安定した色を出すのが最も難しいといわれる「辰砂(しんしゃ)」に取り組んでいる。人間の手でなくては作れないもの。美しい色彩、造形を生み出す人間の手。手仕事の尊さと色彩に対する創造力を喚起する映画。 『緑の海平線 〜台湾少年工の物語』 藤田修平 2006年/60分/カラー/VIDEO 監督:郭亮吟 Liang-Yin Kuo 撮影:劉吉雄 Asio Liu 音楽:Tibor Szemzo 語り:林強 Lim Giong プロデューサー:藤田修平 第二次世界大戦中、日本政府により約8000人の台湾の子供たちが神奈川県にあった海軍工廠に派遣され、日本各地の軍需工場で軍用機の制作に従事した。残された文献や数十人にわたる関係者へのインタビュー、台湾、日本、中国、アメリカでの撮影など4年にわたる制作期間を経て、歴史を多面的に捉え人間のドラマを抑制の取れた形で提示したドキュメンタリー。台湾少年工の忘れられた物語に光が当てられる。 『中村三郎上等兵』 中村のり子 2008年/38分/カラー/VIDEO 監督:中村のり子 撮影:中村のり子、香取勇進、田中絵里 (イメージフォーラム映像研究所 卒業制作) 5年前に死んだ「三郎おじいちゃん」の戦友だったという人からの手紙を見つけた。大好きだったおじいちゃんの戦争体験とはどんなものだったのか…。その過去を確かめたくて、家族や親戚、戦友だった人達に会って話を聞き始める。現代の日常に生きる「私」のおじいちゃんが「中村三郎上等兵」だった頃の様子を知るにつけ、見えてきたものは…。身近なおじいちゃんの中にみつけた戦争をめぐる逸話を撮った。 |
| 「松川賞」授賞式(入賞者シンポジウム・表彰・審査委員の講評) |
|
プログラムG 18:00〜19:40 |
【松川八洲雄監督作品】 『鳥獣戯画』 1966年/24分/カラー/16mm 制作:映像社、七人の会 脚本・監督:松川八洲雄 脚本:大沼鉄郎、杉山正美、杉原せつ、藤原智子、富沢幸男 撮影:瀬川浩 音楽:間宮芳生 語り:芥川比呂志 プロデューサー:富沢幸男、堀田正己 100本近いフィルモグラフィーのうち、松川監督にとって数少ない「自主企画」作品。日本人なら見たことがある「鳥獣戯画」は“マンガ&ジャパニメーションの源流”という解釈もあるが、自由奔放に見える動物たちも、実際に描かれた時代背景…人心は乱れ、末法思想の現れたその時代と並べて凝視すると、楽しそうな動物たちの奥底に別の表情が見えてくる。 国宝・鳥獣戯画の中に、歴史には現れない庶民の姿を見る。 『花の迷宮 〜小原豊雲の世界〜』 1986年/31分/カラー/16mm 制作:岩波映画製作所 企画:小原流 脚本:監督:松川八洲雄 撮影:八幡洋一 音楽:間宮芳生 プロデューサー:高橋昭男、田村恵 「花だけが生けられる“いけばな星人”」小原豊雲氏の人物像と創作風景をSF映画のように記録。初見の方は必ず唖然とすること請け合い。 『神々のふるさと 出雲神楽』 2002年/41分/カラー/16mm 制作:英映画社 企画:ポーラ伝統文化振興財団 監督:松川八洲雄 脚本:菅野均 撮影:小林治、八幡洋一 語り:北村昌子 プロデューサー:宮下英一、内海穂高 神話・伝説の国「出雲」には多くの神楽が伝承されている。佐太神社では、9月24日の夜に古伝の「御座替式」が厳粛に執り行われ、翌25日が例大祭で、「七座」「翁」「佐陀神能」が奉納される。佐陀神能の演目は十二番あるが、最も人気のある曲は「ヤマタノオロチ」の神話を内容とする「八重垣」である。この映画では、「見々久神楽」「奥飯石神楽」の「ヤマタノオロチ」を比較し、さらに新しい表現方法で人気のある石見の「有福神楽」にも視点を当て、出雲神楽の秘密を探ろうとしている。さらに「芸」の歴史を受け継ぐ「地域と人」の歴史も丁寧に映し出されている。 |
|
ゲスト予定者 |
・山田泉さん(元中学校教諭) ・時枝俊江さん(「夜明けの国」監督) ・池内了さん(宇宙物理学者) ・筑紫哲也さん(ジャーナリスト) ・井上修さん(「出草之歌」監督) ・森まゆみ さん(作家) ・まつかわゆま さん(シネマアナリスト) ・日向寺太郎さん(映画監督) ・内海穂高さん(映画プロデューサー) ・野村正昭さん(映画評論家) ・清水浩之さん(映画祭コーディネーター) |
| →プログラムはこちら |
TOPへもどる